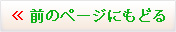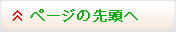すすめる会通信 NO.206

コロナ禍で語る 非正規問題の今は…
最初にパネラーの菊池悦子さんが「どうして私は輝けないのか・個人の問題=社会の問題・コロナ禍と非正規シングル女性」を自身の非正規体験から話し始めると、会場は一気
にテーマに集中しました。 岩永先生は、菊池さんの話を受けるように、日本の「貧困」問題、「コロナショックの被害は女性に集中-雇用回復の男女格差-」と社会に潜む問題をえぐりだしました。 トーク&トークに移ると、次々に手が上がり、当事者の切実な発言が続くのは昨年ではない光景でした。自分のことを語ることに臆せず、具体的な状況が語られたのは、それだけコロナ禍で状況が逼迫しているのだと思えました。★大庭裕子(中原区)、大西いづみ(宮前区)、赤石ひろ子(多摩区)の3市議からも非正規問題を市政に届けるという発言が。
すすめる会通信 NO205
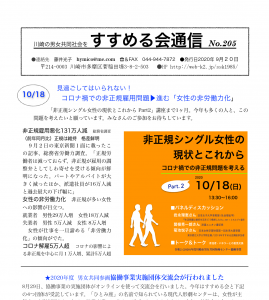
非正規雇用悪化131万人減 総務省調査(前年同月比)正規は維持 格差鮮明 9月2日の東京新聞1面に載ったこの記事、総務省労働力調査。「正規労働者は減っておらず、非正規が雇用の調整弁としてしわ寄せを受ける傾向が鮮明になった。パートやアルバイトが大きく減ったほか、派遣社員が16万人減と過去最大の下げ幅に」 女性の非労働力化 非正規が多い女性への影響が目立つ。
就業者 男性29万人増 女性18万人減 失業者 男性 5万人減 女性 8万人増 女性が仕事を一旦諦める「非労働力化」の傾向がでた。
すすめる会通信 NO.204
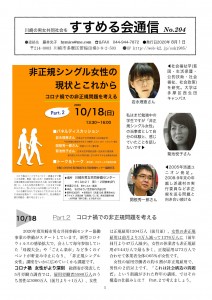
2020年度川崎市男女共同参画センター協働事業の準備がスタートしています。新型コロナウィルスの感染拡大で、会として毎年参加していた「母親大会」や「ごえん楽市」など多くのイベントが軒並み中止になり、「非正規シングル女性」講座をいかに広めていくかも課題です。
コロナ禍 女性がより深刻 総務省が発表した5月労働力調査では、雇用労働者5580万人のうち男性は3000万人(前月より+1万人)、女性 は正規雇用1204万人(前月並)、女性の非正規雇用は前月より3万人減って1376万人に(前年同月より47万人減少)。女性の休業者も非正規雇用が144万人で最も多く、正規雇用は73万人で合わせて休業者全体の65%が女性です。
女性の雇用労働者の約6割が非正規雇用で、男性の2倍以上です。「これは社会構造の問題だ」という指摘がされた昨年の講座。ではその構造の仕組みとは? Part.2で考えましょう。
すすめる会通信 NO.203
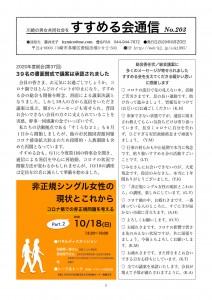
39名の書面賛成で議案は承認されました
会員の皆さま、お元気にお過ごしでしょうか。コロナ禍でほとんどのイベントが中止になり、すすめる会の総会も開催を断念、書面による議案決議となりました。しかし39人の方から返信をいただき議案は成立。暖かいメーセージも寄せられ、普段お会いできない会員の方々に支えられていることを実感、幹事一同感謝の念でいっぱいです。 私たちの活動拠点である「すくらむ21」も6月1日から開館しましたが、他の市民館図書館同様コロナ感染拡大防止のため段階的・人数制限も含めた再開となっています。 すすめる会も、6/1に今度第1回の幹事会を開き、通信による発信を中心に再始動。コロナの状況で開催方法が変わるかもしれませんが、10/18の講座は定員を21名に減らして準備を始めました。
すすめる会通信 NO.200

昨年10月、「女性解放をめざした先輩たちと出会う~フェミニズムを引き継ぐために」と題して、「婦人問題懇話会(会報)」ブックトークを開 催 し た 。 9 0 代 か ら 6 0 代 の 婦 人 問 題 懇 話 会(1962-2001)の元会員たちと、40代から20代の若い世代が、「会報」を材料として語りあった。
参加者は予想外に多く、300名近かった。樋口恵子さんや井上の1960年代、70年代の女性の状況や運動についての体験談に、若い世代が耳を傾け、共感してくれたことはうれしかったが、「思いは受け継がれているが、問題は解決していない」という、若い世代の発言が印象に残った。
すすめる会通信 NO.199
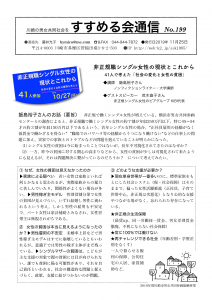
非正規で働くシングル女性が増えている。横浜市男女共同参画センターらの調査によると、非正規職で働くシングル女性の約7割が年収250万円以下、特に45~54才の約3割が年収150万円以下であるという。若年シングル女性の場合、“正社員雇用の経験がなく低賃金で働かざるを得ない” “職場でのパワハラ等の経験からうつになり働けない”などの仕事上の問
題に加え、実家での家族とのトラブルなどの問題を抱えていることが明らかになった。
⑴ シングル女性の貧困は今に始まったことではないが、長年不可視化されてきたのはなぜか?
⑵ 一方、昨今の貧困に対する関心の高まりなどから、女性の貧困が少しは可視化されて来たようにも見えるが、それは問題解決に繋がっているのだろうか? について考えてみたい。
すすめる会通信 NO.198
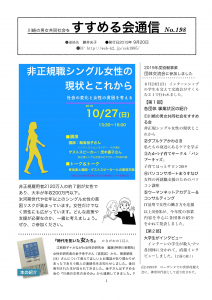
非正規雇用者2120万人の約7割が女性であり、大半が年収200万円以下。氷河期世代や壮年以上のシングル女性の貧困リスクが高まっています。女性だけでなく男性にも広がっています。どんな政策や支援が必要なのか、一緒に考えましょう。ぜひ、ご参加ください。
すすめる会通信 NO.197

「政治分野における男女共同参画推進法」施行後の初めての国政選挙。女性当選者は、政府目標の3割に届かない結果となりました。(投票率48.8%) 女性候補者 104人(全候補者の28.1% ) 女性当選者 28人(当選者の22.6% 前回より-0.5%) 自民党は女性候補の数値目標を設定していませんでした。
すすめる会通信 NO.196

2019 川崎市男女共同参画センター協働事業 3月3日に行われた、協働事業第2次選考会の結果、採用にになりました。非正規で働く人は2036万人、その6割が女性です。40歳前後の非正規労働者が増加して、未婚率も上昇。男性も含めて、シングル女性の壮年非正規労働者の割合が増加しています。
非正規職シングルをとりまく現状や課題について、考えましょう。